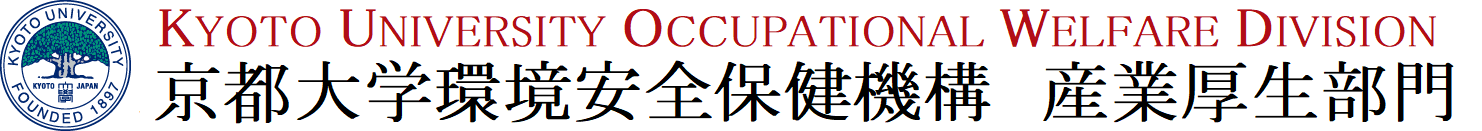沿革
本学の学内措置施設である保健診療所の沿革を紹介する。
学生の保健医療施設として,明治41年(1908)我が国における最初の大学生に対する健康保持のための健康相談と診療業務を目的とした医員室と病室が開設され,大正13年(1924)現在の保健診療所の前身である学生健康相談所が開設された。当時の規模は内科4名,皮膚科,外科各1名,薬剤師,看護婦,事務員各1名にて業務を担当し,眼科,耳鼻科,X線撮影は本学医学部附属病院に委嘱した。
昭和5年(1930)歯科を増設,昭和8年(1933)に整形外科を同附属病院に委嘱し,同年には早くもX線直接撮影装置を購入した。
昭和10年(1935)に耳鼻咽喉科を,同12年(1937)精神神経科を,同じく附属病院に委嘱し,さらには眼科も昭和13年(1938)に増設され,全国にその比をみない立派な陣容が整えられ,入学生,在校生の診療,保健管理に成果をあげることになった。 終戦後,社会一般の健康状態が悪化し,学内教職員のための保健医療施設の設置が要望され,昭和21年(1946)教職員厚生会医療部を本所内に設け,学内教職員並びにその家族の健康相談及び診療を行うことになった。
昭和24年(1949),従来の学生健康相談所を京都大学保健診療所と改称し,学生・職員全員の健康管理と診療を行う施設とし,所属も学生部から事務局に変更された。昭和25年(1950)40歳以上の血圧測定を必須項目とする全教職員に対する定期健康診断を,他大学に先駆けて開始した。同年宇治分校設置に伴い宇治分所を開設した。
昭和33年(1958)学校保健法が制定されたことをうけて,同年度から学生・職員の定期健康診断の検査項目に検尿,検便を加えた。このように早期より,当時としてはかなり充実した保健管理業務を熱心に実施してきたことは,現在の全国大学保健管理発展のために大切な基礎資料を提供することとなった。診療のための臨床検査の増加と放射性同位元素取扱者などの定期的血液検査に対応して,昭和36年(1961)に衛生検査室を増設し,同39年(1964)に精神・神経科を,また同46年(1971)に整形外科を所内に増設した。
昭和41年(1966)4月,保健管理センターの設置に伴い,組織的には保健管理業務は保健管理センターに分離されたが,健康診断の事後措置は勿論のこと,専門医による日常の診療業務から保健管理に必要な情報を保健管理センターに提供している。
本学における保健管理業務は疾病治療,疾病予防,健康保持,健康増進など多岐にわたり,しかも充実したものになっているが,これは上述のように学内諸先輩の努力のたまものであり,また,保健診療所の全面的な協力によって運営されているからである。
近年,国際化とともに疾病構造の変化が認められるとともに,全体的に留学生・外国人研究者の受診が増加してきている。このような変化,すなわち疾病の国際化への対応を迫られているのが現状である。またその特色としては,一般医療施設に見られるような待ち時間の無駄がないよう配慮が行われ,その結果,学生の勉学や職員の業務・研究に支障が生じないよう対応している。 かりに,保健診療所で対処困難な場合は,専門医療機関へ紹介するなどの便宜を図っている。